
座ってじっとしている時間を減らすこと
糖尿病の生活指導の2本柱が食事と運動療法であることからもわかる通り、運動は高血糖の改善に大きな力を発揮します。
筋肉は、体を動かし、体熱を生み出すためのエネルギー源として、血液中のブドウ糖(血糖)を使います。運動をすれば、それだけ筋肉のエネルギー消費量も増え、血液中の余分な糖が筋肉に取り込まれて、血糖値も下がるわけです。
加えて、筋肉をよく使うと、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きもよくなります。
現代人の大多数を占める2型糖尿病は、インスリンはじゅうぶんに分泌されているのに、その指令を受け取る細胞の受容体の働きが鈍り、インスリンがうまく効かない状態になっています。これを「インスリン不耐性」といいます。
ところが、運動で筋肉を使うと、インスリン受容体が活性化し、インスリンがよく効くようになって血糖値も下がりやすくなるのです。
座ってじっとしている時間を減らすこと
とはいえ、運動が嫌いな人や苦手な人にとっては、新たに運動を始め、それを習慣化するのは、なかなかハードルが高いことです。「運動しなければいけない」と考えること自体がストレスにもなりかねません。
しかし、ウォーキングやジョギング、水泳など、特別な運動だけがすべてではありません。
私たちは、日常生活の中で、家事や仕事をしたり、通勤・通学のために歩いたりと、さまざまな生活活動を行っています。それらも運動と同じく身体活動(筋肉の収縮を伴い、安静時よりも多くのエネルギーを消費する状態)であり、高血糖の改善に役立ちます。

わざわざスポーツクラブに通ったりしなくても、日常生活の中で体を動かす機会を増やすだけでもじゅうぶん、運動になるのです。
日常の身体活動がどれくらいの運動に相当するかを知る目安に、厚生労働省が出している「METs(メッツ)」という指標があります。
これは、安静時のエネルギー消費量を1として、それぞれの活動が安静時の何倍のエネルギーを消費するかを示したものです。
例えば、立って料理や片づけをすれば消費カロリーは安静時の2倍に、犬の散歩や部屋の掃除をすれば3倍以上に増えます。
身体活動量を増やすコツは、とにかく、座ってじっとしている時間を少しでも減らすこと。立っている時間を1日2時間増やすだけで、インスリンの働きは3割ほどアップするとの研究報告もあります。
下にあるMETsの数値別に示した活動内容を参考に、どうぞご自身の日常の身体活動を見直してください。そして、こまめに動く「血糖コントロールによい体の使い方」を身につけていきましょう。
身体活動量を表すMETs(メッツ)とは?
METsとは、身体活動の強度を示す指標。
人が安静にしている状態を1METsとして、さまざまな活動が、その何倍のエネルギーを消費するかを表している。
運動だけでなく、多くの生活活動(日常生活における家事、労働、通勤・通学など)についてもMETsが算出されており、活動の強度としては2METs以下が「低強度」、3METs以上が「中強度以上」とされる。
「METs×時間×体重(kg)」の計算式で消費カロリーを算出でき、例えば体重50kgの人が3METsの活動を1時間行った場合は「3(METs) ×1(時間) ×50(kg) = 150(㎉)」となる。
厚生労働省は、健康維持のために「3METs以上の身体活動を1週間に23METs・時(※)以上行う」ことを推奨している。
※METs・時 = METs×運動時間(h)
3METs未満の活動(身体活動・運動量の基準値の計算に含めないもの)
| METs | 活動内容 |
|---|---|
| 1 | 静かに座って(あるいは寝転がって)テレビ・音楽鑑賞、リクライニング、車に乗る |
| 1.2 | 静かに立つ |
| 1.3 | 本や新聞等を読む(座位) |
| 1.5 | 座位での会話、電話、読書、食事、運転、軽いオフィスワーク、編み物・手芸、タイプ、動物の世話(座位、軽度)、入浴(座位) |
| 1.8 | 立位での会話、電話、読書、手芸 |
| 2 | 料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯物を洗う、しまう、荷作り(立位)、ギター:クラシックやフォーク(座位)、着替え、会話をしながら食事をする、または食事のみ(立位)、身の回り(歯磨き、手洗い、髭剃りなど)、シャワーを浴びる、タオルで拭く(立位)、ゆっくりした歩行(平地、散歩または家の中、非常に遅い=54m/分未満) |
| 2.3 | 皿洗い(立位)、アイロンがけ、服・洗濯物の片付け、カジノ、ギャンブル、コピー(立位)、立ち仕事(店員、工場など) |
| 2.5 | ストレッチング*、ヨガ*、掃除:軽い(ごみ掃除、整頓、リネンの交換、ごみ捨て)、盛り付け、テーブルセッティング、料理や食材の準備・片付け(歩行)、植物への水やり、子どもと遊ぶ(座位、軽い)、子ども・動物の世話、ピアノ、オルガン、農作業:収穫機の運転、干し草の刈り取り、灌漑の仕事、軽い活動、キャッチボール*(フットボール、野球)、スクーター、オートバイ、子どもを乗せたベビーカーを押すまたは子どもと歩く、ゆっくりした歩行(平地、遅い=54m/分) |
| 2.8 | 子どもと遊ぶ(立位、軽度)、動物の世話(徒歩/走る、軽度) |
3METs以上の生活活動(身体活動量の基準値の計算に含むもの)
| METs | 活動内容 |
|---|---|
| 3 | 普通歩行(平地、67m/分、幼い子ども・犬を連れて、買い物など)釣り(2.5(船で座って)~6.0(渓流フィッシング))、屋内の掃除、家財道具の片付け、大工仕事、梱包、ギター:ロック(立位)、車の荷物の積み下ろし、階段を下りる、子どもの世話(立位) |
| 3.3 | 歩行(平地、81m/分、通勤時など)、カーペット掃き、フロア掃き |
| 3.5 | モップ、掃除機、箱詰め作業、軽い荷物運び |
| 3.5 | 電気関係の仕事:配管工事 |
| 3.8 | やや速歩(平地、やや速めに=94m/分)、床磨き、風呂掃除 |
| 4 | 速歩(平地、95~100m/分程度)、自転車に乗る:16km/時未満、レジャー、通勤、子どもと遊ぶ・動物の世話(徒歩/走る、中強度)、屋根の雪下ろし、ドラム、車椅子を押す、子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度) |
| 4.5 | 苗木の植栽、庭の草むしり、耕作、農作業:家畜に餌を与える |
| 5 | 子どもと遊ぶ・動物の世話(歩く/走る、活発に)、かなり速歩(平地、速く=107m/分) |
| 5.5 | 芝刈り(電動芝刈り機を使って、歩きながら) |
| 6 | 家具、家財道具の移動・運搬、スコップで雪かきをする |
| 8 | 運搬(重い負荷)、農作業:干し草をまとめる、納屋の掃除、養鶏、活発な活動、階段を上がる |
| 9 | 荷物を運ぶ:上の階へ運ぶ |
血行をよくしようとする体への働きかけが大事
無理なく楽しみながら、日常生活の中で身体活動量を増やしていくために、ここでは5つのアイデアを提案します。
まず、ソファーに寝そべったり、座ったりで動かずにいる時間を減らし、「立って何かをする」機会を増やすこと。立つだけでも運動強度が上がります。
動かずにいると筋肉が衰える上、血液循環が悪くなり、酸素や栄養、血糖が筋肉に届きにくくなります。血液循環の悪化は、神経障害など糖尿病の合併症にもつながります。そこでたいせつなのが、血行をよくするための体への働きかけです。コリほぐし運動やマッサージ、座っているときにできる手足の「ながら運動」を取り入れて、血流をよくしていきましょう。
多くのエネルギーを消費したり、インスリンの効きが悪い状態を改善したりするには、太ももやお尻、背中、腹筋など大きい筋肉を動かすのが効果的です。私は、立ったついでに壁に手をついて腕立て伏せをしたり、柱につかまってもも上げ運動をしたり、机に手を置いてスクワットをしたりと、「ついで運動」をこまめに実行しています。
ウォーキングなどの有酸素運動は、血液中の余分な糖を消費し、さらに脂肪を燃やす効果もあります。血糖コントロールのために、1日15~30分程度歩くのが理想です。
わざわざウォーキングに時間を割く必要はなく、晴れたついでに、外出したついでに歩く「ついでウォーキング」でじゅうぶん。背すじを伸ばし、顔を上げて、「1、2、1、2……」のリズムを意識しながら元気にテンポよく歩いてみましょう。
コロナ禍で外出の機会が減り、家でゴロゴロと動かずに過ごす時間が増えた人は多いでしょう。体のいろいろなところを、いろいろな方法で動かす。自分の行動や気分、周りの環境も含めて「変化を楽しむ」気持ちで取り組むことが、無理なく日常の身体活動量を増やし、それを習慣化するだと思います。
アイデア①立つだけでも、運動強度が上がる
静かに座っているときのMETsは1なのに対し、立って会話や読書をすると1.8METs、立って料理や洗濯を行うと2METs。つまり、立つだけで運動強度が上がり、エネルギー消費量が2倍に増える。テレビやスマホを立って見る、こまめにイスから立ち上がるなど、家でも職場でも立つ機会を見つけて、「立つだけ運動」を実行しよう。

アイデア②こりをほぐすだけでも、血液循環が改善される
肩こりや腰痛など慢性的な体のこりや痛みは、心身ともにストレスのもと。ストレスはインスリンの働きを低下させ、血糖値が上がる一因に。体のこりをほぐすと血液循環が改善され、血糖値も下がりやすくなる。腰痛には「腰反らし体操」を、肩こりには「あご引き体操」を。こりの原因となる悪い姿勢を正し、痛みをやわらげてくれる。

アイデア③テレビを見ながらでも、神経障害、細小血管の障害を防ぐ
静かに座って過ごすときも、手首や足首をグルグル回すとか、手や足の指をギュッと握ってパッと開く「グーパー運動」など、手足を動かすクセをつけよう。

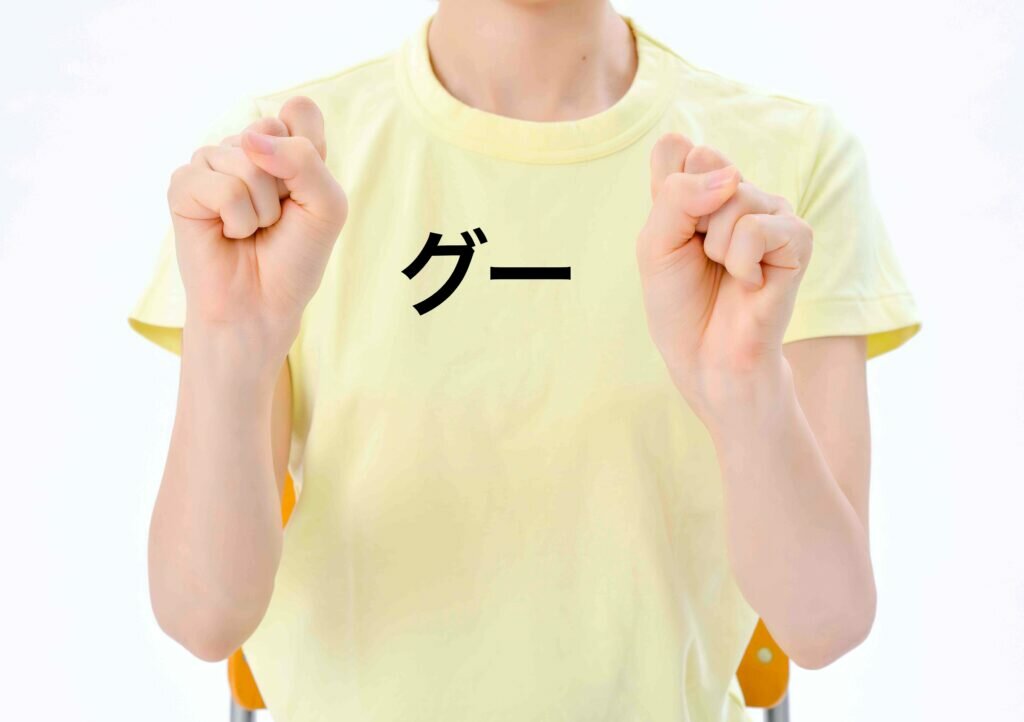
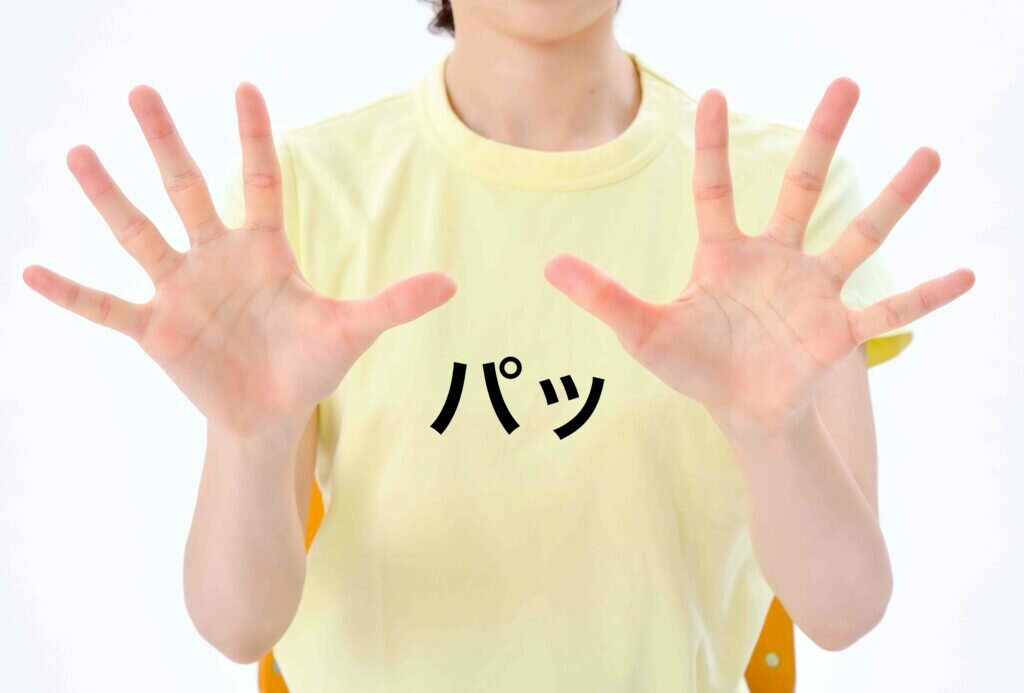
滞りがちな体の末梢の血流を促し、神経障害や細小血管の障害を防ぐ。クルミなどを握って手の中で転がしたり、足下に青竹踏みを置いて足裏を刺激したりするのもいい。



アイデア④大きい筋肉を動かすと、インスリン感受性を改善
太もも、お尻、背中など大きい筋肉はエネルギー消費量が多く、体の大きな筋肉を動かせば、血液中の糖が効率よく筋肉に取り込まれる。筋肉から分泌されるホルモンにはインスリン感受性を高める作用があり、その効果も相まって、血糖値がより安定しやすくなる。スクワットやもも上げ、壁を利用した腕立て伏せなどがお勧め。

アイデア⑤ウォーキングも晴れたついででいい
外出や用事のついでにちょっと歩く「ついでウォーキング」でOK。晴れた日に外を歩けば、骨や免疫力を強化するビタミンDが体内で合成され、「ハッピーホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌も増加する。運動+ストレス解消効果で、血糖コントロールも良好に。自分の行動や心境を含め、「変化を楽しむ」ことが、長続きのコツ。


